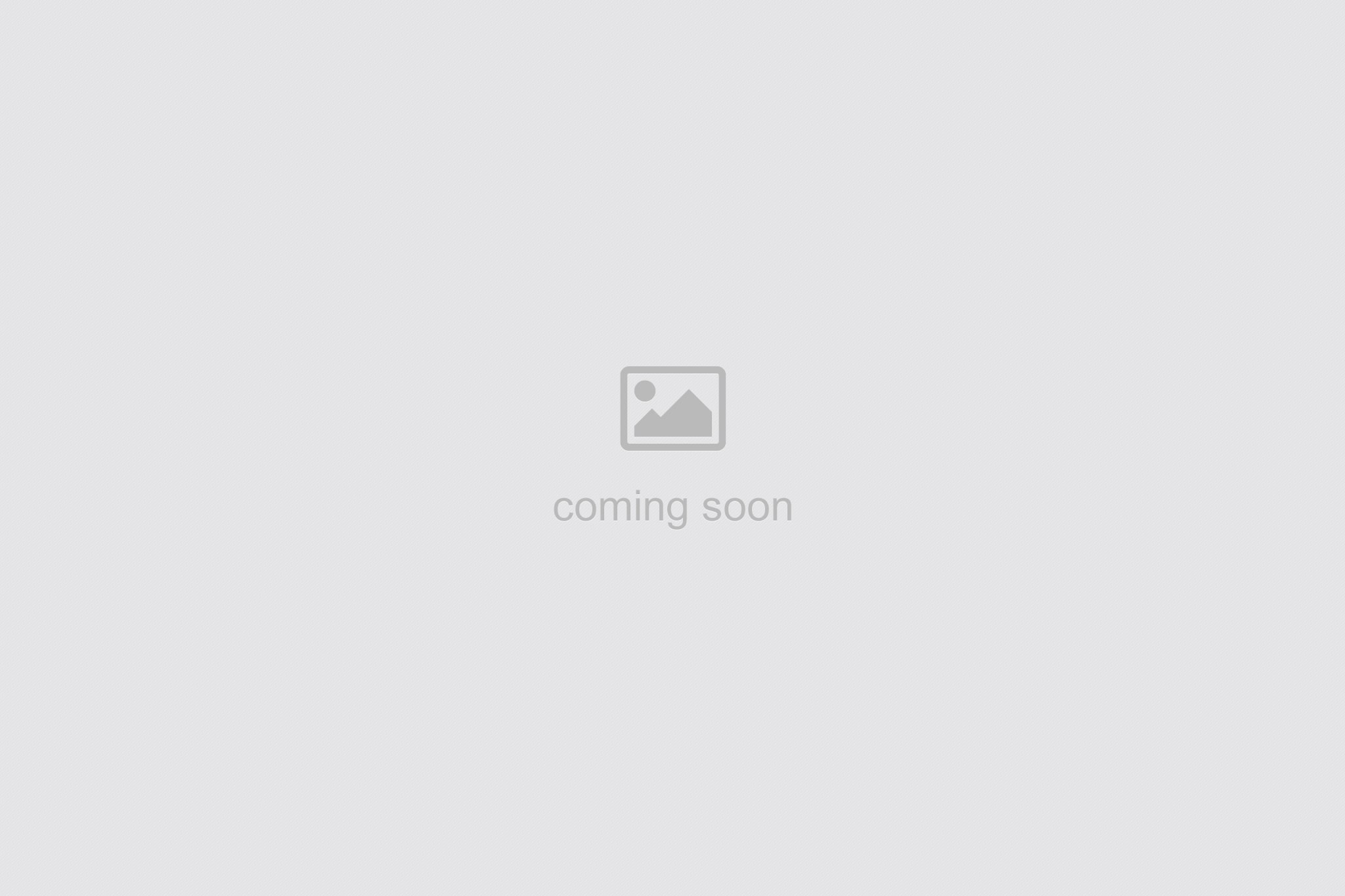胚の凍結保存について
胚盤胞の凍結保存について
今回は「胚盤胞の凍結保存」といわれたけれど
採卵後に培養した受精卵を、受精後1~2日目の「初期胚」より長く培養し、受精後5~6日目の「胚盤胞」まで発育させて凍結保存する方法です。当院では患者様とご相談の上、凍結保存可能な受精卵の個数と、発育状況に応じて「胚盤胞」まで発育させてから凍結保存をしています。
凍結保存できる個数や状態により、一部を「初期胚」で凍結保存し、残りを「胚盤胞」で凍結保存する場合もあります。
凍結保存できる個数や状態により、一部を「初期胚」で凍結保存し、残りを「胚盤胞」で凍結保存する場合もあります。
凍結保存胚-胚移植とは
「凍結保存胚の融解-胚移植法」とは
凍結してある胚を融解(解凍)して子宮内に移植する方法です。
あらかじめ凍結保存してある胚を使用するため、卵巣刺激や採卵を行うことなく、移植が可能です。
凍結保存胚の融解-胚移植法による妊娠・出産がはじめて報告されたのは、1983年で、当院では開院当初より多くの患者様が妊娠・出産しています。
通常の新鮮胚移植と、融解後の胚移植による妊娠・出産を比較した場合、胎児の発育、周産期のリスク、産科的合併症、先天奇形などに関して差はないといわれています。
あらかじめ凍結保存してある胚を使用するため、卵巣刺激や採卵を行うことなく、移植が可能です。
凍結保存胚の融解-胚移植法による妊娠・出産がはじめて報告されたのは、1983年で、当院では開院当初より多くの患者様が妊娠・出産しています。
通常の新鮮胚移植と、融解後の胚移植による妊娠・出産を比較した場合、胎児の発育、周産期のリスク、産科的合併症、先天奇形などに関して差はないといわれています。
[凍結保存胚の融解-胚移植法の方法]
凍結保存胚の融解-胚移植法の治療は大きくわけて以下の2つの方法があります。当院では、主に2の「ホルモン補充周期法」で治療を行っております。
- 自然周期法
ホルモン補充を行なわずに自然排卵の後に胚移植をする方法です。
ホルモン剤を使用しなくてよいというメリットがある一方、月経周期が順調で、自然な状態のままで、子宮内膜の着床環境が良い状態である必要があります。また、移植に最適なタイミングを決定するのに、ホルモン補充周期法と比較すると、スケジュールが立てにくく、通院回数が多くなるというデメリットもあります。 - ホルモン補充周期法 *当院では主にこちらを採用
自然周期を抑えて、卵胞ホルモン(エストロゲン)を投与し、着床環境を整えてから移植する方法です。ホルモン剤の使用が必要になるものの、月経周期が不順な場合や、子宮内膜の着床環境がよい状態になりにくい方には適しています。また、ホルモン補充でコントロールするため、自然周期法と比較して、スケジュールが立てやすく、通院回数は少なくて済みます。
当院ではこちらの方法を採用し、移植する周期の1~2周期前から、低用量のピルを服用し、排卵をコントロールしながら治療を進めています。